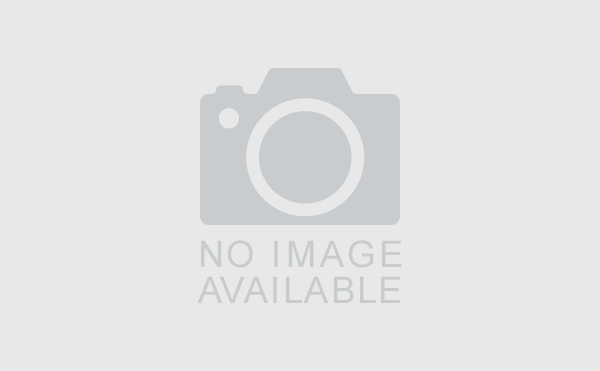15 あれじゃ伝わらないよ
あれじゃ伝わらないよ
これは、私が大学生時代にアルバイトをしていた学習塾のC先生の言葉である。
C先生は、首都圏の某大学を卒業後、都内の大手進学塾である○谷○塚で研鑽を積まれた方である。
その後、郷里の岩手県に戻られ、盛岡市内で学習塾を開業された。
私はその塾のアルバイト講師の第1号であった。
C先生からは、授業の仕方だけでなく、人としての在り方などを教わった。
まさに私にとっての「人生の師」である。
(余談だが、C先生の紹介で入団した合唱団が縁で、現在の妻と知り合うことになる。)
C先生の授業は、「生徒が10人来たら10人が笑顔で帰る」がモットーであった。
それはすなわち、帰り際の生徒たちの表情は、授業の良し悪しを計るバロメーターということを意味していた。
お世話になった当初、私の授業に対する生徒たちの評判はイマイチであった。
それは、帰り際の生徒たちの暗い表情からも明らかであった。
C先生からは、「そんな授業じゃダメだ。」とよくダメ出しをされた。
ある日のこと、生徒たちとの雑談で、タニシには寄生虫がいるので生食が危険であること、そして、かの有名な北大路魯山人氏の死因がタニシの生食であることに触れた(諸説あり)。
生徒たちは私に、「北大路魯山人って誰?」と尋ねた。
私は、「美食家で、陶芸家で、書道家で・・・。」と、通り一遍の説明をしたが、生徒たちは今一つピンと来ていないようだった。
そんな様子を見たC先生は一言、
「美味しんぼの海原雄山みたいな人が実際にいたの。」
と生徒たちに説明した。
生徒たち一斉に、「へー。」と納得し、理解したようだった。
C先生は、「生徒たちの目線で説明しないと。あれじゃ伝わらないよ。」と私に仰った。
私はそのC先生の一言で、「自分が理解している」ということと、「相手に理解してもらう」ということは全く別物であるということを知った。
それから私は、常に「生徒たちの目線」を念頭に置いた授業を心掛けた。
そして、90分間の授業には、「自分の理解のため」に1時間、「生徒たちの理解のため」に2時間、計3時間予習して臨んだ。
それから少しずつ、帰り際の生徒たちの表情も明るくなり、授業に対する評判も上がっていった(気がする)。
私が盛岡を離れ、アルバイトを辞める時、C先生は、「あとは保護者の対応ができれば、この世界で食べていけるよ。」と褒めて下さった。
私は涙が出るほど嬉しかった。そして、ポンコツだった私を長い目で見守って下さったC先生に心から感謝した。
この時の経験は、今でも少なからず役に立っている。
研究内容のプレゼンや、研究費の申請書を作成する時、私は難しい専門用語を(極力)避け、常に聴衆や審査員の目線を念頭に置いている。
以前、テレビで某タレント(漫才師、映画監督、コメンテーター等で活躍)が、
「世代が違うと話が合わないなんて言うのは間違い。話が合わないんじゃなくて、話を引き出せない自分がバカなのだ。」
と云っていた。
C先生にお会いしていなければ、私は(今以上に)バカなままだったのかも知れない。