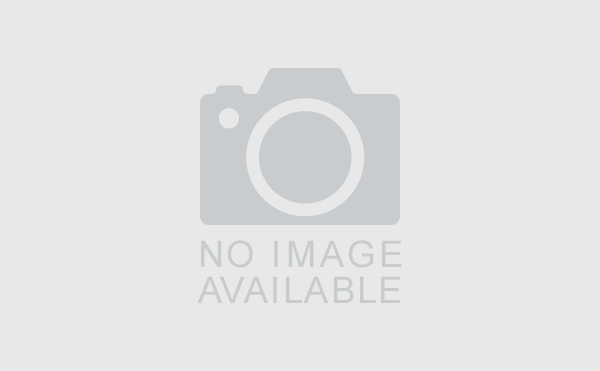7 過去の仕事を見ろ
過去の仕事を見ろ
これは、留学時代の恩師であるP教授の言葉である(もちろん英語)。
P教授は、コラーゲンの生合成や遺伝子異常による疾患などの分野では世界的権威である。
一方で、骨髄由来間葉系幹細胞(骨、脂肪、軟骨への分化能をもつ幹細胞の一種)の発見者の一人として知られ、こちらの分野でも世界的権威である。
90歳近い現在も、多数のスタッフを抱え、ラボヘッドとして精力的に研究を遂行されている。
P教授はメンバーの研究テーマに関して、具体的に「あれをやれ」「これをやれ」とは指示しなかった。
それぞれのメンバーは、自分で研究テーマを見つけ、P教授の潤沢な研究費を使って自由に実験をしていた(許可は得なければいけなかったが)。
裏を返せば、自分の研究テーマに関しては、結果が出なくても「自己責任」ということになる(いかにもアメリカ)。
渡米して日も浅く、研究テーマも決まらずに右往左往していた私に、P教授はこう仰った。
「研究室の『過去』の仕事を見ろ。そして『現在』の仕事を見ろ。そうすれば『未来』、すなわち自分のやるべきことが見えてくる。」
不肖の弟子であった私は、帰国してしばらく経った後、その言葉の真意を理解することになる・・・。
時は流れ、2013年から3年間、私はT大学病院の血液・免疫科に助教として着任した。
診療科長のH教授は、non-MDの私を助教に採用して下さったのみならず、研究の場も提供して下さった大恩人である。
私はそんなH教授の恩に報いるべく、連日トップジャーナルを賑わせていた「造血幹細胞」や「白血病」に関する研究を新たにスタートした。
しかし、「素人の浅知恵」でデータが出せるほど、現実は甘くなかった。
例えるならば、車のギアが「ロー」から「セカンド」に入ったと喜んだのも束の間、また「ロー」に戻るような日々が1年ほど続いた。
そんな私を尻目に、研究室の「番頭さん」的存在のF先生は「トップギア」で研究を遂行していた。
「俺は一体何をしているんだ・・・。」という焦りは、いよいよ私を追い詰めた。
そんな絶望の淵を彷徨っていた私の脳裏をよぎったのは、上記のP教授の言葉であった。
私は、血液・免疫科で綿々と引き継がれていた研究テーマである「間葉系幹細胞」と「多発性骨髄腫」に着目した。
そして、それらの研究テーマに、私が当時手掛けていた「細胞老化」というエッセンスを加えた新たな研究テーマを着想した。
その研究テーマは、幸いにも1報の論文として結実し、H教授の恩にも報いることができた(と願いたい)。
研究(だけでなく物事全般?)は、「新しい流れ」を生むことも大切だが、「すでにある流れ」にうまく乗ることも大切だと知った。